プログラミングには才能が必要?プログラミングの才能がある人の特徴8つ
プログラミングに才能は必要か?

プログラミングに対して専門的な知識やスキルが求められるイメージを抱く人も多いと考えられます。また、センスや才能が求められる分野として認識しがちです。
プログラミングの才能はあった方が有利ですが、努力や勉強が物を言う分野だと主張する声も少なくありません。
今回は「プログラミング 才能」や「プログラミング 才能ない」などのキーワードで検索している方に向け、プログラミングと才能の関係性についてご紹介します。
プログラミングの才能がある人の特徴8つ

上記では、プログラミングという分野に才能が必要かどうかについて考察しました。
確かに、プログラミングはセンスや才能が求められたり、天才的なひらめきによって新たな物を生み出せたりする可能性がある分野ですが、そもそもプログラミングの才能とはどのようなものなのかも気になるところです。
そこで続いては、プログラミングの才能がある人の特徴について考察していきます。
才能がある人の特徴1:楽しむことができる
「好きこそ物の上手なれ」ということわざがあるように、プログラミングを楽しんでできる人は才能がある人と言えます。
プログラミングとは、ひたすらコードなどを打ち、ノウハウなどを調べ続ける作業です。それらが苦痛になったり、ソースコードなどを見るだけでくらくらしたりする方も少なくありません。
そのため、コードなどを見ることを楽しいと感じられる方には、プログラミングへの才能や適性があると考えられます。
才能がある人の特徴2:高い集中力がある
パソコンと向き合って仕事をし続けるプログラミングは、集中力が求められる作業でもあります。また、誤入力などのちょっとしたミスがあるだけでも、想定した動き方をしない場合もあるため、正確な作業が求められるという意味でも、集中力が必要な作業と言えます。
上記のような背景から、高い集中力がある方や1つの物事にのめり込みやすい方もまた、プログラミングへの適正や才能がある人だと考えられます。
才能がある人の特徴3:リフレッシュすることができる
プログラミングは長時間の作業になることも多く、特に集中して何時間も行う場合も少なくありません。
あまりにも何時間もパソコンと向き合っていると、体調などにも影響が出やすくなり、またストレスもたまりやすくなります。
適度にリフレッシュしたり、ストレス発散をコントロールすることも大切です。リフレッシュやリラックスを自分自身でコントロールする能力もまた、プログラミングの才能の一つと言えそうです。
才能がある人の特徴4:ものづくりが好き
プログラミングは、ものづくりでもあると言われています。実物ではないものの、システムやデータなどを生み出す行為のため、何かを生み出すことが好きな方には、プログラミングの才能がある可能性があります。
また、具体的に欲しいものや作りたいものがある人も、プログラミングの才能を持っている人だと考えられます。作りたいなどの感情は、プログラミングをしていく上で大きなモチベーションになるためです。
才能がある人の特徴5:論理的な思考ができる
どのコードを入力するとどんな動きをするのか、理論的に予想して行動する力が求められる点もプログラミングの特長です。
また、プログラミングにはエラーやバグがつきものとも言われています。問題が起こったり予想通りの動きをしなかったりした時に、感情的にならずになぜエラーになるのか、理論的に考えていく思考が求められます。
上記のような背景から、理論的思考の持ち主はプログラミングの才能があると考えられます。
才能がある人の特徴6:発想の柔軟性がある
プログラミングを行う上で、柔軟な思考や発想は重要です。さまざまな角度から物事を見たり考えたりすることが、エラーの解消に繋がったり、コードやシステムなどに新たなひらめきを与えたりする可能性があるためです。
1つの視点や理論のみで考えていると、いつまで経ってもエラーが解決できず、プログラミングが進まないケースもあります。固定観念などにとらわれない柔軟な発想と広い視野を持つことが、大切です。
才能がある人の特徴7:調べたり質問したりすることに躊躇いがない
プログラミングは、検索や調査の連続でもあります。ソースコードを調べたり、エラーの原因を調査したりしている時間の割合は多く、検索などを行う機会が少なくありません。
ですから、細かく調べたり分からないことをゼロから学んだりすることが好きな方は、プログラミングへの適正が高いと考えられます。調べるための手間や時間を惜しまない方も、プログラミングの才能がある方と言えそうです。
才能がある人の特徴8:学習の意欲が高い
コードなどは無限にあり、日々進歩していくものです。そのため、1回覚えたから良いというものではなく、常に学んでいく姿勢が大切になります。
上記のような背景からも言えるように、プログラミングは学習の連続です。そのため、分からないことを学ぶことや勉強することが好きな人には、才能があると考えられます。
プログラミングに向いていない人の特徴4つ

上記では、「プログラミング 才能ある人」などで検索している方に向けて、プログラミングに向いている人や才能がある人の特徴についてご紹介しました。
続いては、反対にプログラミングに不向きと考えられる人の特徴を考えていきます。
不向きな方の特徴を学ぶことで、プログラミングをするのに大切なことや求められることが見えてくる可能性もあります。ぜひ参考にしてみて下さい。
向いていない人の特徴1:行動力がない
プログラミングは実際にコードを打ち込んでみることが重要です。できると思っていたことが実際に打ち込んでみるとエラーになったり、意外と良い結果に結びついたりすることもあり、実際にやってみなければ気付けないことも沢山あります。
そのため、行動力や自発性がない方は、プログラミングに不向きである可能性が考えられます。
向いていない人の特徴2:パソコン操作に慣れていない
パソコンはプログラミングを行うのに欠かせない存在です。プログラミングとは、コードにより指示を出すことでパソコンにさまざまな動作をさせ、システムなどを開発する行為のため、パソコンの操作に不慣れな方は、プログラミングには不向きと言えそうです。
パソコンの操作に不慣れでも挑戦自体はできますが、1つの動作やステップを行うのに説明書を見たり調べたりしなければならず、作業の進みが遅くなる可能性があります。
向いていない人の特徴3:デスクワークが苦手
パソコンと向き合って行う動作は、基本的にはデスクワークです。そのため、プログラミングもまた、デスクワークだと言えます。
長時間にわたってパソコンと向き合ったり椅子に座ったりすることが苦手な方は、プログラミングへの適正が低いと言えます。
集中してデスクワークができないと、作業がなかなか進みません。
向いていない人の特徴4:勉強が苦手
プログラミングのスキルや技術は日々新しいものが生まれ、進化しています。そのため、プログラミングをする上で新しい技術の勉強や今覚えているコードについての復習などは欠かせません。
勉強が嫌いな方は、スキルなどが定着しない上、新しいコードなどを覚えられないため、プログラミングには向いていないと考えられます。また、調べたりテストを繰り返したりすることが苦手な方も、プログラミングの適正は低いと言えそうです。
プログラミングの学習方法3つ
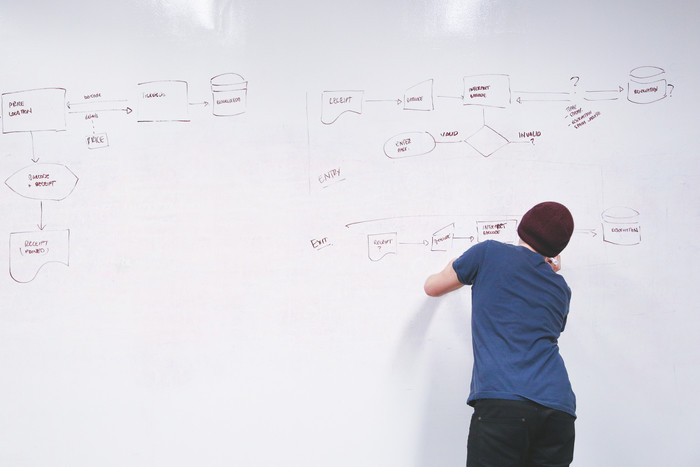
上記では、「プログラミング 才能 ない」などのキーワードで調べている方に対してプログラミングに向いていない方の特長などについて考察しました。
向き不向きはあっても、意欲さえあればプログラミングは誰でも挑戦できるものでもあります。
そこで続いては、プログラミングをこれから学んでみたい方に向けて、勉強方法や学び方についてご紹介していきます。
プログラミングの学習方法1:書籍で学習する
手軽にプログラミングを学ぶ方法としては、書籍が挙げられます。ネット社会となったこともあり、現代ではプログラミングを学ぶための本が多数出版されています。
万が一挫折した時もコストが低いので安心なことから、まずは学んでみたいという方には書籍での学習がおすすめです。しかし、分からない部分などを質問することができないため、挫折しやすい学習方法とも言えます。
プログラミングの学習方法2:Webサイトを活用する
インターネットが普及したことにより、プロや趣味でプログラミングをしている人がWebサイトを運営し、テクニックやノウハウを紹介しています。そのため、検索すればWebサイトからもプログラミングを学ぶことが可能です。
また、オンラインでの有料サービスなども展開され、利用料や入会金を払えば、動画などでプロのプログラミング講座などを視聴して学ぶこともできます。
プログラミングの学習方法3:スクールで学習する
本格的にプログラミングを勉強したい場合や、プログラマーとして働きたい場合は、プログラミングに特化したスクールに通って学ぶのが良いと言われています。
入学金や受講料などが発生するため、費用はかかりますが、プロから直接プログラミングを学べるため、身につきやすい学習方法でもあります。
プログラミングの才能がある人の特徴を知ろう

今回は「プログラム 才能」などでプログラミングの適正などについて調べている方に向けて、プログラミングの才能がある人や向いていない人の特徴、プログラミングの学び方をご紹介しました。
プログラミングは向き不向きが分かれるもののため、確かに才能やセンスは重要です。しかし、不向きであってもやる気や意欲があれば、身につけられる可能性はあります。自分の性格を理解してプログラミングと向き合っていくことが大切です。