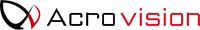IT業界きっての縁の下の力持ち「運用保守」とは
はじめに
IT業界においては様々な職種がありますが、花形と言えばやはりプログラマーやSEのイメージが強いでしょうか。一方、運用保守というと言葉だけでは業務内容がイメージし辛く、多少地味な印象があるかもしれません。しかし、実はIT業界の縁の下の力持ちとして、無くてはならない業務を担っています。「運用保守」の定義は、現場に依存し、多少の違いはあるかと思いますが、大前提の目的としてはいずれもシステムの安定稼働であると言えます。それでは、まず簡単に運用と保守それぞれの業務内容を確認していきます。
運用保守の定義
「システムが正常に稼働しているかどうかを、日々システムを動作させることにより監視する」のが「運用」で、具体的にはサービスを円滑に届けるために、サーバの起動や停止、定時にデータを入力したり等、定型化された業務を確実に遂行していくことでシステムを監視し、状態の把握を常に行うことが主な業務です。一般的には、障害発生時には、手順書に従い暫定的な対処を行うことで、サービスを提供している状態維持を行うのも運用の業務の一部であるようです。また、「メンテナンスやアップデート等の導入を行うことで、システムの改修や調整、修理をする」のが「保守」です。運用と大きく違う部分として、システムに対して変更を加える点が挙げられます。バグの改修やDBのチューニング、サーバ機器等のリプレースも保守の作業範囲であるようです。また、時として機器の故障や想定外の動作など、発生自体が予測し難い事象への対応も、保守担当者の重要な役割と言えます。運用保守業務それぞれの主な業務がお分かりいただけたでしょうか。いずれもシステムを安定稼働させるための業務を担っているわけですが、これらの知識や技術を持っていることで、エンジニアを目指す上でも有利に働くスキルを身に着けていけるのではないでしょうか。したがって、続いては運用保守の仕事内容をさらに詳しく見ていきます。
システム理解に役立つ運用業務
まず、システムの監視を行うことが主な業務である運用担当者の仕事内容について、いくつか見ていきます。主なものとしては、システムを定時に起動及びシャットダウンする「システムのON、OFF作業」や、定期的な「データのバックアップ作業」、ログを確認したりメモリの状態をチェックし、システムが正常に動いているか監視を行う「システム稼働監視」、ウイルスなどにより外部からの攻撃や情報流出の発生は無いか等をチェックし、担当者への報告を行う「セキュリティ監視」等も重要な業務です。その他、作業者が誰でも運用を行えるように手順書をまとめる作業や、効率の良い運用方法が発見出来た場合は業務改善を図り、手順書を作り直すなど「運用手順書」をまとめる作業等も運用担当者の業務と言えます。全体的に監視業務である点が目立ちますが、これは、現代の通信経路や制御システムなどの構成が、非常に複雑且つ規模も大きいことが起因しています。背景としてインターネットの普及やグローバル化、仮想技術・クラウド技術の発展があります。そういった大規模なシステムを設計書等のドキュメントだけで理解するためには、エンジニアとしてそれなりに経験を積んでいなければ難しいものです。しかし上記で挙げたような監視業務では、システムを構成するネットワークやサーバ機器、OS、サービスなどを監視します。したがって、どの機器がどの様な役割で、どの様な通信により、どういったサービスを提供しているのか等、多種多様な構成を業務の中で覚える事が出来るのです。つまり監視を主とする運用業務はシステムの理解に有効な手段と言えます。
システム構築に役立つ保守業務
続いて、システムの改修や調整を行うことが主な業務である保守担当者の仕事内容についてですが、分かりやすいもので言うとシステムに変更や修正が必要な場合の「システムアップデート」や、「新しいプログラムやシステムのインストール」、システム運用担当者から不具合の報告を受けた際に原因の究明を行う「バグ調査」等があります。システム異常やシステムダウンが起こった場合には、「システムの復旧作業」を行います。全体的な特徴としては、対応を定型化できないような問題を運用担当者から引き受け、根本の解決に至るまでの高度なスキルが要求されます。システム設計に従った構築を行う場合には、どの作業がどの通信や、どの機能・機器に対して影響を及ぼすのか等を認識している必要があります。そのために構築検証を必ず行ったり、有識者による手順レビューが繰り返し行われることが一般的です。つまり、構築作業者として熟練度を上げるためには上記のような保守業務を行う事が最適と言えます。作業の手順書や、実機検証を業務の中で覚える事が出来るため、システムの構築を理解するためには保守業務が有効な手段と言えます。
まとめ
運用保守業務は、ITの発展や進化が身近になった現代においても、プログラマーやSEが行うような革新的な発明などと比べて、あまり日常で実感することの無い職種であり、どちらかと言えばIT業界の中でも裏方なのかもしれません。ただし、大規模なシステム障害の解決を行うのは運用保守の役目であり、障害の発生が事前に食い止められているのも運用保守のおかげなのです。そういったことからも運用保守を緻密に遂行してくれているエンジニアがいるからこそ、現代のIT社会が破綻することなく進展し、システムが円滑に稼働していると言っても過言ではありません。言わば運用保守担当者はIT業界の「縁の下の力持ち」であり、さらなるIT社会の発展には今後もますます需要が高まってくる職種であると言えます。